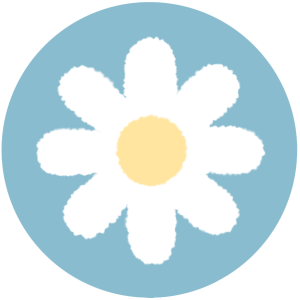石牟礼道子『十六夜橋 新版』を読んだ感想
石牟礼道子『十六夜橋 新版』(ちくま文庫)
第三回紫式部文学賞受賞作。
不知火の海辺の地で土木事業を営む萩原家を中心として、その現在と過去が継ぎ目もなく語られていく。
生きている登場人物だけではなく、すでに亡くなっている人も文字の中にいきいきと姿を蘇らせ、その思いが痛いほど届く。それがひときわ悲哀を感じさせる。
読み始めてしばらくは儚く美しい物語だと思っていたけれど、最後には不思議とそういう感想は残らなかった。もっと複雑だった。
石工、漁師、船頭、僧侶、遊女……一言では語れないそれぞれの人生を読んでいくうちに、その切実な思いの中に人間らしい営みの数々を見つけていった。
裏方となって家を守る男性たちの存在が、物語の支えにもなっていてよかった。
最初、騒がしい宴会のシーンから始まるためどことなく荒々しい印象を持ったけれど、中には守りに長けた男性も数名登場するのが興味深い。一人一人の心をひらいて性格を示していくところがよい。実直でしなやかな強さと奥ゆかしさを備えた人物にはやはり好感を持った。
心惹かれる人物を挙げだすとキリがないくらい、魅力的な人物が多い。
特に当主の妻である志乃が印象に残る。盲目で、病により半分は夢の中に生きている様子で、彼女自身はあまり多くを語れないのにも関わらず存在感は最も強い。
生と死に区別がなくなっているけれど、次第に夢か現かなんてどちらでもよいと思えてくる。
解説によると、作者の祖母がモデルになっているらしい。なにかと祖母の世話を焼く孫も登場する。これは実際に祖母のお供をするのが仕事だったという作者自身の反映がある。
この話は本物の手触りがして作り物ではないと思えたのは、明確にモデルがいるからなのかもしれなかった。
実際の人生のようにすべて同時進行で、物語の筋といったものはあまりはっきりしていない。それでもぼんやりと浮かんでいた祖母、娘、孫の曖昧な関係に、ひとつの答えがあらわれて胸が締め付けられた。
次の世代に引き継がれていくところをずっと読んでいたかった。名残惜しい。